三田評論に掲載されました!【演説館】リバーブランディングの視点から地域と環境を見直す 2025/11/13
私の仕事は、リバーブランディングを通じて、川と地域のオリジナルの価値を創造し、豊かな自然を守り、地域を元気にする活動を進めることです。民間企業、地方公共団体、地元有志の方々などと協業し、「川を守り、活用し、集客する」ことを目指しています。
そして、地球温暖化と、進行する人口減少。これらの問題を解くのは、生命地域主義や自然資源の共有の精神にもとづいた地方創生。地域を流れる川を「コモンズ=新しい公共」として捉えなおし、生活と結び付いた事業として創業することです。
私が掲げる生命地域主義とは、それぞれの地域に存在する自然資源や、文化・歴史・技術などの人的資源を組み合わせ、地域独自の価値をつくり上げていくこと。その地域独自のオンリーワンの価値を皆で考え、共に活動して、地域を元気にしていくこと、この活動の積み上げが過疎化への対策の決め手となります。そんなリバーブランディングを検討しています。
12年前、川をテーマに人生のセカンドステージを楽しみたい、生涯の仕事にしたいと思い活動を始めました。それ以前から自分の理想の川を妄想したり、非現実的な山の暮らしに憧れていましたが、気がついたら勤めていた広告会社でのフィールド活動も後半戦、アディショナルタイムに突入間近になり、”川に飛び込む”ことを決めました。「生涯の仕事」などとは及びもつかないレベルのビジネスモデルでしたが、意を決して日本中の川を歩いて廻りました。
そして株式会社B•M•FT出版の大橋正房相談役のご厚意により、日本のさまざまな地方のこと、川のこと、そして「自身の想い」をまとめた著書『川から始める地方再生──リバーブランディング』を出版していただく幸運に恵まれました。
地方再生活動は待ったなしの課題、その活力の源は川
川は流れることで膨大な生命と生態の循環をつくり出しています。尊いすべての命の源であり、私たち人間の生活に密着し、人々の暮らしを支え、多種多様な生物たちを育んでいます。川たちはいったい、どれだけすてきな郷土文化を日本中につくりだしたのでしょうか。
一方、日本中の川を巡ってみて、現実を知りました。ダムや堰堤が多く、しかも壊れているところが放置されているので、多くの場合、自然資源の生態系が損なわれています。自然再興や生命地域主義に世の中が大きく舵を切ろうとしているさなか、それらと逆行するような多くの現実と出会いました。
そんな中でふと気づいたのは、伝統を守ることは進化であるということです。ご当地に太古の昔から連綿と続く伝統産業や文化には、きわめて卓越した自然との共生のノウハウがあります。
いいかえると、地域資源として自然生態系を利用するには、その維持回復のための地域プログラムによる循環型システムを構築することと、新しい産業技術と情報発信の基盤を持ち外部との交流を実現すること、六次産業化の発想が大切であるということです。
治水や利水を優先するあまり、川に対する対策や警告には、首をかしげたくなるようなものが多く見られます。地方公共団体は何を考えているのだろうかと思うこともありますが、何よりも大切なのは、すべての人が、水の循環や生活ゾーンの川流域について正しい知識をもつことだと思うようになりました。
人間は生まれながらに水の循環に参加しています。その連鎖は、住地域から河川流域、川を通して海まで、そして地球全体に影響を及ぼします。
川は日本の国土の血管
川が健康を取り戻すことは重要なポイントだと思っています。とくに毛細血管(小河川)の血流はとても大切です。スムーズな血流であれば、日本中の各地にたいへんよい循環が生まれ、地域循環型の経済につながります。
台風や線状降水帯による水害の視点からだけではなく、まず日本の文化的な視点から、環境課題において大切な温暖化対策や森林破壊、食糧問題などにどう向き合っていくべきかを考えられると思っています。
日本各地には、3万5000本以上の川があります。その川の数だけ、地域の魅力を発揮できる可能性があります。これは地方創生のための地域ブランディングの差別化ポイントになるのではないでしょうか。
川を大切にすることは地域の良さや特徴を再認識することであり、新しい社会システムの可能性が芽生えることだと期待します。川をみんなの共有資源と考えること、防災を目的に川を封じ込めるのではなく、多くの地域文化や伝統を育んだ生業を思い起こし豊かに共有することが、いま求められる新しいコモンズの発想だと考えています。その共有化には知や情報、技術などのテクノロジーの融合がとても大切です。
地域循環型の経済再生を、着眼大局しながらも着手小局で実現していく。そこに求められるのは、コモンズの精神と地域リーダーの誕生だと考えています。地球温暖化と人口減少は待ったなしの状況です。ここで重要になるのが「コモンズ=新しい公共」の考え方で、モチベーションを高められるビジョンづくりが大切です。住民や企業、そして行政が「ともに考え、ともにつくり、ともに育てる」ことがベストかもしれませんが、現実は甘くありません。地域を憂う誰か一人のリーダーの、強い意志から始まることがスタートだと思います。
それでは、健康な川とは本来、どのような川なのでしょうか。私は「生きている川」と表現していますが、タテ・ヨコ・鉛直方向の連結がとれている川です。
源流から海までつながっていて豊かな生態系や水質が保たれており(タテ)、氾濫できるスペースがあることにより増水時に生物たちにとって好ましい物質交換ができていること(ヨコ)。産卵できる川であること。川底の通水がよく酸素が豊富で微細粒子で目詰まりしていないこと(鉛直)などが理想です。
それは言いかえると、中小河川の多くは”人間に整備されている川”ということになります。
しかし、日本には素晴らしい景観の川は数多くありますが、生物多様性の豊かな「生きている川」は多くありません。川を基点に、自然の命の奥深さを見つめるのもおもしろいものです。
なかなかできることではありませんが、せめて「タテ・ヨコ・鉛直方向」の連結で生きている川によみがえることを知ってもらいたい。それも源流から河口までの全体最適が望ましいですが、現実的には不可能な箇所も多いので、せめて部分最適だけでも検討して、実現してほしいと思います。

自由に蛇行しながら流れている川(『川から始める地方再生』より)
バイオリージョナル公園とは
バイオリージョナル(BR)公園とは、皆さんの生活の場所につくる、地域特性を反映した公園のゾーンコンセプトです。バイオ=生物(学)、リージョナル=その地域特有、の公園です。コンセプトマップを活用して、好きなように公園ゾーンを散策し、楽しみます。
BR公園はなにも日本有数の豊かな自然でなくてもいいのです。三面護岸の川でも、そこで逞しく生きている生物の観察でもいいのです。何といっても人新世(後述)が話題にのぼる時代です。人間の負の歴史が一掃されて新しい環境で生きている動植物を観察することは、訪れる人々にとってかえって新鮮かもしれません。
そして、生物多様性や生命地域主義をわかりやすく見学できる場所は、子どもたちやこれから自然科学を学びたい学生たちにとって、素晴らしい学びの場となることでしょう。
ただ、BR公園への集客の意識を地元住民や有識者が共有することが大切です。
環境の視点からすると、生命地域主義の視点はとても大切です。自治体や町村など行政上の区割りではなく、地理的・生態系的にみた地域の特徴から決まる古くからその土地に根差した固有の文化は、河川の流域を中心に発生する場合が多いのです。それはその地域特有の植物相や動物相をもつ地理的空間であり、自然の様相によって左右されるために柔軟性と可変性を持っています。行政区域が生態系的分断の原因にならないようにコモンズの発想で守られることを切に願っています。
人新世とは?
人新世とは地質学の言葉で、人類の活動が地球の地質や生態系に影響を与えた、現代を含む時代区分を指します。その特徴は人類の活動によって生じた地球温暖化などの気候変動、大量絶滅による生物多様性の喪失、人工物質の増大、化石燃料の燃焼や核実験による堆積物の変化などとされています。このように人類が地球の地質や生態系に与えた負の影響は計り知れませんが、私たちはそんな現実の中で地球環境に向き合っていかなければなりません。
ひとつ事例を紹介しますが、西日本の中規模河川のダム上流域には、陸封されているのにアユの生態系ができつつあります。しかも漁業資源としても期待できるほど安定しています。
本来、アユは海と川を行き来する魚類ですが(一部、琵琶湖などの湖産アユを除きます)、そこのアユたちは降海することなく、閉鎖区域で一生を終え、次世代にその子孫を継承しています。たくましく進化しているアユのことを思うと、人間も自然の一部と考えること、独善的なふるまいを慎むことを同時に肝に銘じなければと思います。
最後に
日本中の多くの川がなぜ壊れたのか?
その答えは簡単です。ほとんどの人たちが地域の川に興味を示さなかったことや環境を軽視したこと、自然が繊細であることを知らなかったこと、災害の視点では自然の力を甘く見ていたことです。いまからできること、やるべきことを地域ごとにどのように決めて、実現するか。生命地域主義は、とても大切な考え方です。地域を憂う有能なリーダーのもと、その地域独自のオンリーワンの価値を皆で考え積み上げることが、過疎化への対策の決め手となります。もちろん、着眼大局しながらも着手小局で。
地域コミュニティが魅力的であること。そのカギは”水の循環”への参画ではないでしょうか。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
![世界に誇る日本の川を見なおす。カワリバ[WaterS Revital PJ.]](https://kawariva.com/wp/wp-content/themes/kawariva/img/logo.gif)







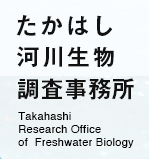
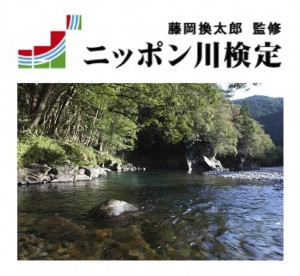

![世界に誇る日本の川を見なおす。カワリバ[WaterS Revital PJ.]](https://kawariva.com/wp/wp-content/themes/kawariva/img/logo_s.gif)

下記 三田評論オンラインもご覧ください。
https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/speaking-hall/202511-1.html
【三田評論 本文】
水谷 要(みずたに よう)NPO 法人ウォーターズ・リバイタルプロジェクト代表・塾員